おはようございます、Rikiseiです。
最近、皆さんの職場ではいかがでしょうか? 年度末の慌ただしさで、ついつい自分の仕事に集中しがちになり、隣の席の同僚の顔を見る余裕すらない……なんて方もいらっしゃるかもしれませんね。
「見返りを求めない『共有』が、あなたの仕事と人生を豊かにする」
なぜ今?
現代社会は、個人の能力や効率性が重視され、私たちは常に「自分で何とかしなければ」というプレッシャーの中で生きています。多くの情報が溢れ、ツールも進化しているのに、なぜか孤独感や閉塞感を覚える人が増えているのではないでしょうか?
それは、効率や経済合理性だけでは満たされない、人間本来が持つ「つながりたい」「助けたい」「助けられたい」という根源的な欲求が置き去りにされているからかもしれません。心の孤独はストレスを増大させ、パフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
だからこそ今、私たちは、フィジーの地に古くから伝わる「ケレケレの精神」に学ぶ必要があるのです。
って、実はたまたまフィジーの本を読んで感化されただけです。そのフィジーの本は最後にご紹介しますね!
Story(実例)
数年前、ある企業で新規事業の立ち上げプロジェクトが進行していました。メンバーは皆優秀で、各自が専門分野を徹底的に深掘り。まさに「各自が自分の持ち場を完璧にこなす」という方針で進められていました。しかし、個々の成果は出ていても、プロジェクト全体としてはなかなか歯車が噛み合わず、情報共有は進まず、各メンバーは「自分の担当部分で手一杯」と孤立感を深めていきました。あるメンバーが体調を崩し、その業務が完全にストップしてしまった時、プロジェクトは危機に瀕しました。
一方、フィジーの村では、誰かが困っていれば、見返りを求めずに隣人が手を差し伸べます。例えば、誰かの家の屋根が壊れたら、村中の人が集まって修理を手伝い、収穫期にはみんなで畑作業を分かち合います。彼らは競争するのではなく、互いを認め、支え合うことで、物理的にも精神的にも豊かな暮らしを築いています。この「助け合い」の精神が、彼らのレジリエンス(回復力)を高め、どんな困難も乗り越える力になっているのです。
もし、先のプロジェクトチームが、フィジーの「ケラケラの精神」を持っていたらどうなっていたでしょうか? 互いの進捗や課題を積極的に共有し、専門外のことでも「何か手伝えることは?」と声をかけ、小さな困りごとが大きくなる前に、誰かがそっと助け舟を出していたかもしれません。結果として、プロジェクトは停滞せず、メンバーの心も健康に保たれていたでしょう。
Principle(原理・型・ルール)
フィジーの「ケレケレの精神」、つまり「無償の共有文化」は、現代のビジネスシーンにおいても驚くほど強力な原理として機能します。
- 認知負荷の軽減と切替コストの削減:
仕事効率化のコツで「認知負荷理論」や「バッチ処理」の重要性をお話ししましたね。人間は、たくさんの「開いたタブ」(未完了のタスクや情報)を抱えていると、一つのタスクにかける集中力が落ちます。また、タスクを頻繁に切り替える(コンテキストスイッチ)と、そのたびに集中力を再構築するコストがかかります。
ケラケラの精神は、この「認知負荷」をチーム全体で分散し、削減する効果があります。誰かが困っている情報を「共有」することで、その問題を抱え込んでいる個人の「開いたタブ」を閉じ、代わりにチームの誰かがその「タブ」を開く。あるいは、共同作業として「バッチ処理」的に一気に解決することで、個々の切替コストを大幅に減らすことができます。 - 内発的動機の強化とレジリエンスの向上:
人間は、他者に貢献することで「役に立っている」という承認欲求だけでなく、「貢献そのものから喜びを得る」という内発的動機が満たされます。これは、外からの報酬(給料や評価)以上に、持続的なモチベーションにつながります。
また、チーム全体で「助け合う」という文化が根付くと、個々人が孤立することなく、心理的安全性が高まります。誰かが困難に直面した時でも、「一人じゃない」という安心感が得られ、チーム全体のレジリエンスが向上し、予期せぬトラブルにも柔軟に対応できるようになるのです。
Practice(今日の一手・ミニタスク)
では、今日からあなたの仕事に「ケラケラの精神」を取り入れるための、具体的なミニタスクを3つご紹介します。
- 「ワンワード助け舟」を出す:
もし同僚が眉間にシワを寄せていたら、たとえ直接関係ない仕事でも「何か困ってることありますか?」「何か手伝えそうなこと、ひょっとしてあります?」と、わずかワンワードで声をかけてみましょう。目的は解決することではなく、「気にかけている」というメッセージを伝えることです。 - 「10秒知識共有」を実践する:
あなたが最近学んだこと、発見した効率化のコツ、あるいはちょっとした業界ニュースなど、チームメンバー全員にとって有益かもしれない情報を、チャットや朝礼で10秒で共有してみましょう。完璧な資料や深い洞察は不要です。「これ、面白いなと思ったんです!」くらいの軽い気持ちでOKです。 - 「感謝の連鎖」を意識する:
もしあなたが誰かに助けてもらったら、必ず「ありがとう」を伝えてください。そして、その感謝の気持ちを他の誰かに「パス」するつもりで、今度はあなたが誰かを助けてみましょう。感謝は最高のエネルギーです。
落とし穴&条件
「ケレケレの精神」を取り入れようとすると、「見返りを期待してしまう」「自分の仕事が増えるだけでは?」「偽善だと思われたらどうしよう」といった落とし穴に陥りがちです。
これを機能させるための条件は、たった二つです。
- A. 期待を手放す: 助けた相手からの見返りは期待しない。「与える喜び」そのものを報酬と捉える。
- B. 「完璧でなくていい」と割り切る: 完璧な助けや、自分の専門分野外のことで悩む必要はありません。ほんの小さなことでも、あなたの気遣いや行動が、誰かの心を温め、大きな変化を生むことがあります。
まとめ一行:
要は、与える喜びが、最高のモチベーションとなり、チームを強くする。
今日の課題(3点)
- 今日、仕事中に「この人、ちょっと困ってるかも?」と感じた同僚に、自分から声をかけましたか?(Yes/No)
- あなたの仕事で得た「小さな発見・コツ」を、10秒で誰かに共有しましたか?(Yes/No)
- 過去に誰かに助けられた経験を一つ思い出し、その時どんな気持ちだったかを思い出してください。
クロージング:
さあ、今日からあなたの職場に、フィジーの温かい「ケレケレの精神」を広めてみませんか? きっと、あなたの仕事も、そしてあなたの人生も、これまで以上に豊かなものになるはずです。応援しています!
さて、今回私がこうしたことを考えるきっかけになった本がこちらです。
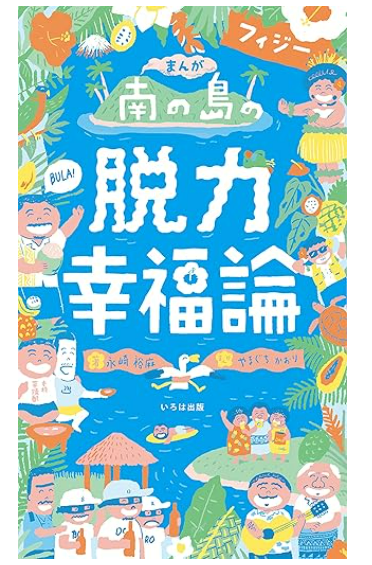
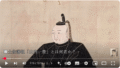

コメント